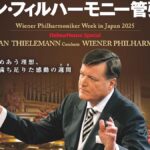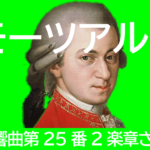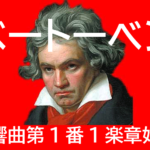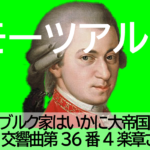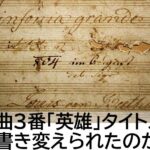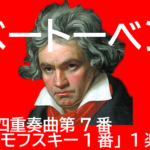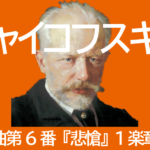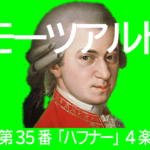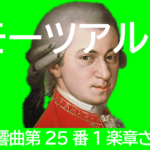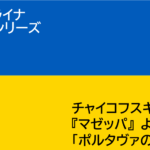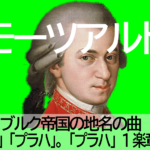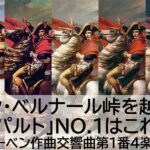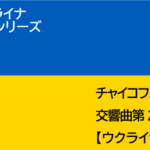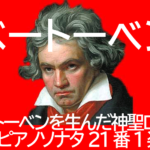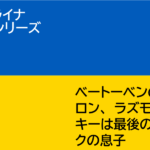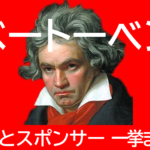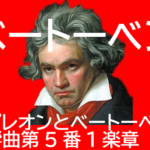グスターボ・ドゥダメル指揮
ロサンゼルス・フィルハーモニック に行ってきた。
曲目は
J. アダムズ:Frenzy(狂乱)[日本初演]
ストラヴィンスキー:バレエ組曲『火の鳥』(1919年版)
ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』
新曲と、ストラヴィンスキー・びっくり箱シリーズだ。
びっくり箱ポイント1は『火の鳥』
びっくり箱ポイント2は『春の祭典』
さあ、どんなふうにびっくりさせてくれるのか。
ストラヴィンスキー:『火の鳥』
『火の鳥』はロシアの民話からのお話。
王子が火の鳥を捕まえる。火の鳥は逃がしてくれた王子に幸運の羽をあげた。
王子はカスチェイの魔法でとらわれていた王女と恋をし、助けに向かい危機が訪れた時、羽を取り出すと火の鳥が助けてくれた。おかげで魔法がとけ、王子と王女は結ばれる、というストーリー。
魔王カスチェイの凶悪な踊り
やはり。山場は王子と魔王カスチェイの戦いの場面、曲でいう5番目の「魔王カスチェイの凶悪な踊り」で、ここがびっくり箱ポイント1。
この曲に入る時のドゥダメルが「行くぞ! 行くぞ!! GO!!!—–」という感じで力強く腕を振り飛び跳ねて、「ジャン」と大フォルテのところからの入りが激しく炸裂して、椅子からちょっと浮くくらいびっくりした。
そして、ファゴット、からのトランペット、金管がガリガリと差し込んできて迫力だ。
だがしかし。弦の存在がもう一つ。薄くてボリュームを感じない。
フルートももう少し”煽り”があってもよかったのかなと思った。
魔王カスチェイの凶悪な踊り
ロサンゼルス・フィルは金管のオーケストラなのだなと思った。
トランペット、トロンボーン、チューバが容赦なしにハキハキ、バリバリと空気を切り裂き最高に気持ちがいい。
ヴァイオリンは癖なく優しい感じだ。
序章 今回目を見張ったのが、コントラバスが9台。左後方をコントラ軍団的が陣取っていた。
この軍団が小さい小さい音から入るわけで、これがとても厚みがある。贅沢だ。
弦が。弦をこする奏法(?)「シャリシャリシャリ」と鳴らすところがあるが、ここを見て聴くのを楽しみにしたが、思いのほかあっさりであった。
火の鳥の踊り ここはフルートから弦、ハープと鳥が飛び回る様子が聴きどころであるが、ここももう一つパート同士の受け渡しの連携が単調な感じでヒュンヒュンとしたすばしっこさがなかったように思う。
終曲
ホルンのソロ。いい音だ。ヴァイオリン、フルートも効いている。トランペット、トロンボーン、チューバ、そしてティンパニのバズーカ砲で最高に盛り上がって、少しクラクラした。
スピード感とエネルギッシュなお囃子的なサウンドがドゥダメルとぴったりだった。
オーボエが全体を支える芯となる強く輪郭のはっきりしたよい音であった。
ストラヴィンスキー:『春の祭典』
『春の祭典』と日本語のタイトルだが、本当におぞましい設定の曲だ。
若い女性を祖先の霊への捧げものだなんだといいながら、要するに老人たちの餌食にするという話である。
第2曲 春の兆し(乙女たちの踊り)
びっくり箱ポイント2。
9台のコントラバスが「ザザザザザザ、ザザンザザザン」とくるところ。
トランペット、ファゴット、トロンボーンはきっぱりした音で「嫌~な感じ」を煽り立ててくれるのだが、弦が薄く、びっくり度はもう一つであった。
第2曲 春の兆し(乙女たちの踊り)
第3曲 誘拐
トランペットがもう見事。
割れたような、破裂したような、ビリビリと超ド級にすごい。
お2人なのだが、オーケストラのキングという感じ。
第5曲 敵の部族の遊戯
ここはティンパニ。凄みのある恐怖の音だ。
そして、ホルン。ホルンは、ソフトな音から強く硬い音と同じ楽器なのかと思うほど色合いが違う。
トロンボーン、チューバもバリバリでかっこよい。
The ブラス&パーカッションオーケストラだ。
長老たち、祖先
長老たちや祖先云々の数曲は、もういやらしくて気分のよくない曲である。
もっさりして不気味。
ところがドゥダメルだとそのようにならない。
不気味さ陰鬱さはありながら、アクセント、強弱、スピードコントロールで各パートが力強くかみ合って、生命力がみなぎった演奏で次・次と世界に引き込まれた。
第14曲 生贄の踊り(選ばれし生贄の乙女)
なにが”選ばれし”だ。
抵抗、哀しみ、絶望、残酷さ、断末魔。理不尽に汚され人生を台無しにされる乙女の最悪災難をどうしてくれるのか。
ドゥダメルは細かく細かくパートに指示を送り、出るところ押さえるところを明確にして、歯切れよく密度高くそして暗さ・悲壮感が充満する演奏であった。
最後はブラスとティンパニの大渦潮にのみこまれ、しびれた。
ジョン・アダムズ:Frenzy(狂乱)
前後するが、最初に演奏されたのがジョン・アダムズ作曲のFrenzy(狂乱)。
ロサンゼルスフィルが委嘱した作品で2023年に作曲されたものだそう。
これがよかった。
現代のストラヴィンスキー?といった様相。
素人には難しい複雑なリズムにのって各パートがバラバラにいろいろな音を様々なタイミングで出していてそれがまとまっている、という感じ。
「狂乱」とはまさにそう。
難解ではあるのだが、ドゥダメルはリズムをラテン的(?)に活き活きとさせ各パートの良き音を際立たせていて楽しかった。
委嘱作品というと、たいてい一回でいいかなという風であるが、この曲はドゥダメルだったらもう一度聴いてみたい。
ドゥダメルは、話かけるように手・腕・全身、身のこなし、顔の表情で指揮をしていて、聴いているだけでもノッてくる。
今回、おもしろかったのは、開始時間30分ほど前からすでに団員の多くの方々は舞台に上がって、リラックスして音出しをされていた。
コントラバスやハープの方がそうされていることはあるが、ほぼ全員が、というのは珍しいのではないか。
曲の性質上、楽器を温めておくということなのか、楽屋スペースが狭いのか、そういったことは知らないが、観客としてはうれしい。
開演前の注意事項アナウンスが入ると静かにされるのも、おもしろかった。
※写真はAMATIウェブサイトより
2025年10月24日 サントリーホール