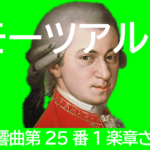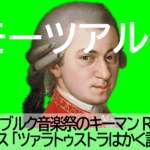ウィーン・フィルハーモニーのコンサートに行ってきた。
指揮は、トゥガン・ソヒエフ。
予定されていたフランツ・ウェルザー=メストさんがご病気のためのスペシャルピンチヒッターだ。
曲目は
リヒャルトシュトラウス:交響詩『ツァラトゥストラはかく語りき』
ドヴォルジャーク:交響曲第8番
クライマックスが一番最初の「日の出」
ソヒエフが登場し、指揮台に昇る。
その時から会場のだれもが身じろぎもしない。
最初の最初、コントラバスの”地鳴り”が生まれ出でるその瞬間を聴き逃すまいと耳を凝らし息を凝らし緊張感がみなぎっているからだ。
それはもう自分の血流の音が聞こえてしまうんじゃないかと思うくらいだ。
ソヒエフが手を上げてついに”地鳴り”が始まった、すごいすごいこのように始まるのか、響くのかと小さくとも意外と力強いコントラバスの世界に入った。
そして、くる。トランペットだ。
暗いくらい闇の中で一筋の鋭い光が差し込んでくる、どんな光だ、と期待を膨らませていた。
ところが。「あれ?」と感じた。
ウィーンフィルの煌びやかで突き抜けてくるトランペットを想像していたが、曇り気味の音であった。
ティンパニーは迫力で、またソヒエフのちょっとアクセントが独特かなという楽しさがあり、気を取り直したところで次の「背後世界論者へ」と移っていった。
全体、もちろんボリューミーで重層的なハーモニーが規律正しく繰り広げられるのだが、パートごとの輪郭や、リヒャルトシュトラウスのストーリーに合わせた変化は、そう特徴付けられていないように聴いた。
ハープの「ポロロロン」と入るところを注目していたがなんとなく過ぎてしまった。
ソヒエフは一つ一つの音符や休符を繊細に編み合わせた仕上がりが素敵だと思うが、今回、それがもう一ついきわたっていなかったのか、それが味付けなのか。
コントラバスとチェロとの低音の弦は人生の深淵と強さを描き出すように響き震えた。
トロンボーンはキレがあって太い響き。
コンサートマスターのライナー・ホーネックさんの「舞踏の歌」のソロは美しい。まろやかで、みずみずしく聴き惚れた。
The素晴らしい ドヴォルジャーク8番
ドヴォルジャーク8番は、すごかった。神様ありがとうございます、という時間だった。
ヴァイオリンは変幻自在、ソロ楽器のバックにまわるときは品のいい小人たちのように一つになって正確で美しい音で支え、ヴァイオリンがメインのところはふわーっと柔らかく、空中に浮くかのような甘い音色が拡がってくる。
特に3楽章のメランコリックな旋律のところは
芳醇なコーヒーの香りが鼻からとおって体内に回り、脳内に充満していくかのようにうっとりしてしまう。
別々のパートがソヒエフを中心にテンポ、強弱、息遣いなどが有機的に一体化し会場が満たされた。
4楽章はブラスだ。
トロンボーンが吠える、ホルンがこぶしで唸る、フルートがうたう。
ああ、もう4楽章を何度でも永遠に聴いていたいー。
ひと足早いニューイヤーコンサートが来てくれた!
なんと、アンコールをそれも2曲やってくれた。
J. シュトラウスⅡ世:ワルツ『芸術家の生活』
J. シュトラウスⅡ世:ポルカ・シュネル『雷鳴と稲妻』
ブゥオーーーーとドヴォルジャーク8番を演奏していた方々が、同じメンバーですか? という感じで「ズ・チャッチャ ズ・チャッチャ」と一気にウィーン風に変身。
東京でウィーンフィルを聴けて、ニューイヤーコンサートも聴けるという最高に贅沢な空間で感激だった。
生「雷鳴」には撃たれた。
個人のミーハー的視点からは、ヘーデンボルク・和樹さん、 ヘーデンボルク・直樹さん、チェロのブルーがいらしてうれしかった。フルートがカリンもカール・ハインツさんの姿もみえなかったのがちょと寂しかった。
リヒャルトシュトラウス:交響詩『ツァラトゥストラはかく語りき』「日の出」
最初聞こえないくらい小さい。
ドヴォルジャーク交響曲第8番3楽章
J. シュトラウスⅡ世:ポルカ・シュネル『雷鳴と稲妻』
(2023年11月19日 サントリーホール)