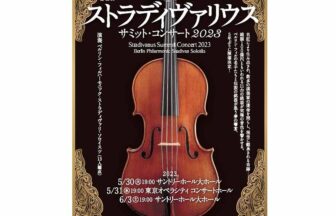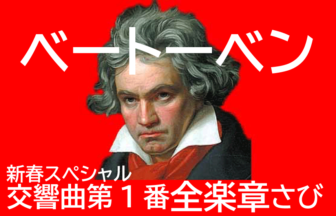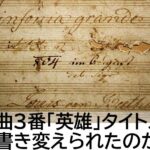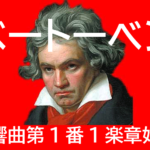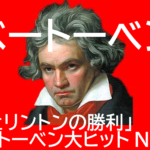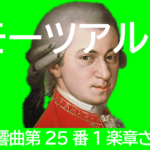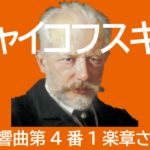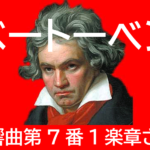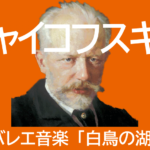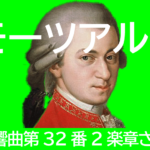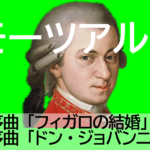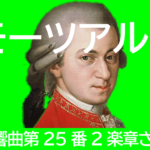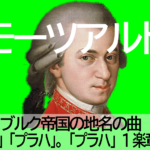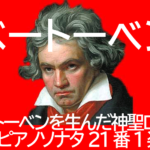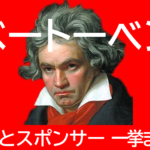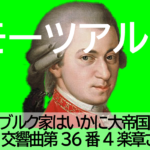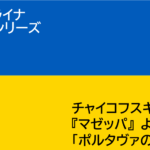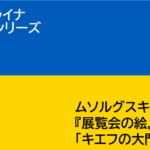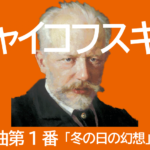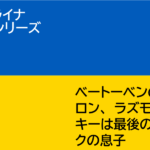ヴォ―チェ弦楽四重奏団 ベートーベン4番,11番,12番 に行ってきた。
曲目は
ベートーベン:弦楽四重奏曲 第4番
ベートーベン:弦楽四重奏曲 第11番
ベートーベン:弦楽四重奏曲 第12番
第4番、スタートが「落ち着いて聴かせてくる」のか?「勢いでつかんでくるのか」?と思っていたら。なんと「柔らか」だった。
ふわっと4人全員が同じ羽根布団に載っているようにテンポと強弱がピタリと合って心地よい。
うわぁぁ、いいなぁとワクワク耳をすませていたが・・・。
ここまでだった。
なんだかピタッときていない。
特に思いっきりフォルテになってくるともはやバラバラな感じ。
今回は1stのヴァイオリニストが病気で来日断念とのことで、急遽助っ人でコンスタンス・ロンザッティさんが加わったとのこと。
メンバーが違っても果敢に攻めてくる感じは伝わるが、バランスがうまくない。
やはり影響があるのかなと。
今回1stヴァイオリンを務めたセシル・ルーバンさんはクセのない素直なサウンドで強弱の表情がとても豊か。
最高潮のときには、足を踏み鳴らしながらの熱演奏でかっこよかったが、いかんせん少し線が細いように感じた。
第11番では、コンスタンス・ロンザッティが1stを担当された。
伸びのある元気で夏にあう音色だ。
4人の息もだんだん合ってきた。
ヴィオラのギヨーム・ベケールさんが、いい。
リズムがあふれた硬質な音で、ほかの3人を引っ張っている。
右端(客席からみて)に位置し、ヴィオラが出るところでは、楽器を会場の方に向け音を拡げてくれる。
あとで、ウェブサイトをみたらチェロの方も変更があったようだ。
ベケールさんがチェロの役割も果たしたのかなと思った。
それぞれが個性的で魅力ある演奏だが・・。これらが噛み合わさってこその弦楽四重奏団の魅力なのだということを改めて認識した。
ルーバンさんが、今日がツアーの最後で疲れ気味と話されていた。
2人も(半分!)メンバーが変更になり、最後はベートーベン3本とはほんと、どれだけ大変でらしたかと思う。
お疲れ様でした、とたくさん拍手をしてきた。
アンコールはラヴェル 弦楽四重奏曲 第2楽章。
ヴォ―チェはパリ国立高等音楽院で結成されたユニット。フランスの作曲家の曲に力を入れているとのこと。
サッと空気が変わる透明感のある生き生きとした演奏。
たくさんのピチカートが弾けまわって素敵だった。
今度は、ヴォ―チェ通常のメンバーで。そしてロンザッティさんの本職で、聞いてみたい。
ベートーベン:ヴァイオリン四重奏曲第4番出だし。
演奏:パガニーニ四重奏団 1949年録音
ラヴェル:弦楽四重奏曲 第2楽章
演奏:ジュリアード弦楽四重奏団 1959年5月18日録音
※写真は武蔵野市民会館ウェブサイト、新潟市民芸術文化会館ウェブサイトより。
2024年6月15日 武蔵野市民文化会館小ホール